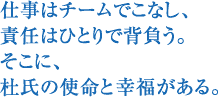| ≫歴史と浪漫 人吉、そして繊月酒造の歴史と浪漫 ≫繊月に込められた味の秘密 ≫焼酎と火の国くまもとの味覚 ≫月の噺 |
|
| ≫ほろよいびとトップへ |

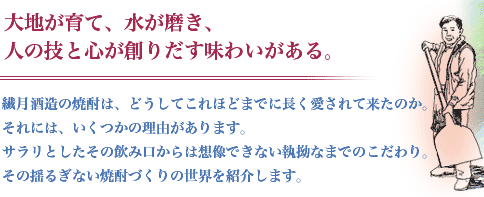

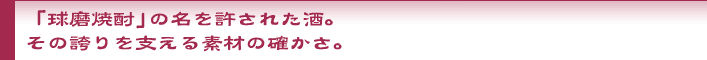 |
||
 |
 |
「球磨焼酎」。この何気なく使われている呼び名の向こうには、私たちの焼酎づくりに欠かせない確かな真理がひそんでいます。 実のところ、球磨・人吉地方でつくられる焼酎のすべてがこの名で呼ばれる訳ではありません。つまりこの酒は、「単に球磨という地域で生産される焼酎」ではないのです。ここに、「繊月」の旨さに関わる大きな要素、すなわち“素材”という問題が横たわっています。 |
|
焼酎の味を決定づける第一の素材は、仕込みに使われる水。そして「球磨焼酎」とは、仕込み水に球磨川の伏流水を使っていることを絶対の条件としているのです。 もちろん、当社も例外ではありません。メインブランドの「繊月」をはじめ、「峰の露」「舞せんげつ」「たる繊月」などで使われる水は、すべて球磨川の伏流水。これを濾過して仕込んでいます。 ちなみに、“地産地消”をテーマに掲げて開発された「川辺」や「しろいし」「葦分」などの地域限定ブランドの場合は、その地域の良質の水と米を使うことで個性を引き出しています。とはいえ、まったく初めての素材で焼酎をつくるのは、どんな酒蔵にとっても至難の業。この難しい作業を乗り越え、新ブランドを次々に開発できたのも、杜氏たちの長年の経験と素材への深い理解があったからのことなのです。 |
||
 |
||
 |
米へのこだわりも、欠くことのできないポイントです。 繊月酒造で使われる米は、地元九州でとれた「ヒノヒカリ」。その質の善し悪しは、杜氏がひと目見ただけで分かるといいます。 粒がそろっているか。乾燥の期間は適当か。質にばらつきはないか……。一切の妥協に背を向けたプロの誇りを、情熱とその重さを、この純白のひと粒ひと粒が静かに語りかけてくるようです。 |
|
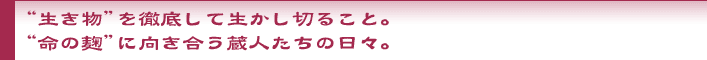 |
||
 |
 |
「麹こそ命」。焼酎づくりの現場を率いる5代目杜氏・越冨茂が、いつも口癖のように語っている言葉です。 米を洗い、蒸して、冷ます。これに種麹を混ぜ、“繊月酒造の麹”として丹念に育てていく。できあがった麹に仕込み水と酵母を加えて一次もろみが造られ、これを熟成させ、さらに米を洗い、蒸して、冷ます。これに種麹を混ぜ、“繊月酒造の麹”として丹念に育てていく。できあがった麹に仕込み水と酵母を加えて一次もろみが造られ、これを熟成させ、さらに掛け水を加えて発酵。二次もろみに育てていく。これを加熱蒸留して、焼酎に仕上げていく。……と、文章で表せばわずか数行ほどのこの作業に、文字どおり命を賭けて取り組んでいるのが越冨杜氏率いる蔵人(くらこ)たちです。 麹菌を米の芯までまんべんなく繁殖させるためには、まず適切な蒸し加減が不可欠。そして麹の育成には、執拗ともいえるほど細密な温度管理が求められます。 |
|
「麹は、一回一回、口に入れて確かめながら、完璧な状態のものに造りあげます。温度管理は季節ごとに変わる気候との闘い。ちょっとでも気を抜いたら命取りになるとです」。 “生き物”だからこそ、その力を充分に生かし切って最高の味をめざす。そんな決意を秘めた越冨杜氏の言葉です。 |
||
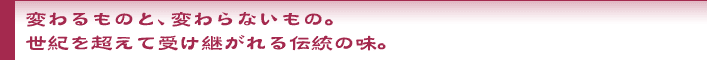 |
||
 |
昨年4月、当社は峰の露酒造から繊月酒造と改称しました。明治36年の創業以来100年。この間に機械化も進み、酵母や麹の開発も進歩したおかげで、焼酎づくりの現場は大きく変わっています。 たとえば、3代目杜氏の淋豊嘉の時代は、草履を履くと雑菌がつくからと、凍えるような冬の日でも裸足で仕事をしていたとか。いまからは想像もできないほどの重労働だったのです。 その頃の様子を伝えてくれるのが、いまも蔵の入口近くに置かれている「もろぶた」や「暖気樽」などの道具たちです。これらは、30年ほど前まで使われていました。 こうした道具類のほとんどは、杜氏や蔵人たちが自ら考案し、自らの手で造ったものです。現在でも、「麹寄せ」や「櫂棒」などはそうして使われています。 「機械が入ってきて、現場の作業自体はずいぶん楽になりました。でも、だからといって焼酎づくりが簡単になったわけじゃない。相変わらず麹の管理は難しいし、機械の限界も当然ある。杜氏を続けている間はこの重圧から逃げられないと、そう覚悟しとりますよ」(越冨杜氏) |
 |
 |
||
 |
現代の名工。それは、ものづくりに携わる者にとって最高の誉れといえるでしょう。その栄誉に醸造の世界で初めて輝いたのが、当社の3代目杜氏・淋豊嘉です。 昭和2年(1927)、入社。昭和55年(1980)に亡くなるまで有形無形の功績を残した大人物でした。その有形の功績のひとつが、40年前から蔵の甕に眠っている大古酒です。 |
 |
| 単に貴重な酒というだけではありません。なによりも、その完成度の高さによって、多くの左党たちから「球磨焼酎の宝」と言われている傑作。初代・横井宇作の時代から連綿と受け継がれてきた伝統の神髄を、いまに伝えています。 | ||
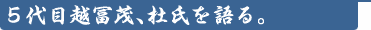
 |
 繊月酒造は、創業の当初から杜氏と蔵人をきちんと社内に置いて製品づくりを続けてきました。そのため、100年を経たいまでも高度な技術が確実に受け継がれ、安定した味と品質を守っています。 初代杜氏・横井宇作は、明治人らしい実直な気風で、焼酎づくりの先鞭をつけました。2代目の大瀬甚蔵は、”一徹の人”。杜氏としての自信と威厳を存分に発揮しながら、当社の明治・大正・昭和を牽引し続けました。 このふたりが磨いた技術は、3代目・淋豊嘉の才能を得て一気に開花。「現代の名工」の名にふさわしい無数の功績を生み出すのです。さらにこの達人の薫陶を受けて、4代目・重富武春が「繊月」を完成。そして、そんな先人たちの偉大な個性と息づかいが残るこの蔵で、いま5代目が伝統を受け継ぎつつ新たな挑戦を続けています。 「いまでもつくづく、『大変な仕事を引き継いだものだ』と思います。杜氏になって5年、気の休まる日は一日もありませんでした。いまでもふと気になって、夜中に工場に出てくることもありますよ」(笑)
そう語る越冨杜氏が、なによりも大切にしているのが蔵人たちのチームワークです。 |

|
|
| Copyright(C) Sengetsu shuzo. All rights reserved. |