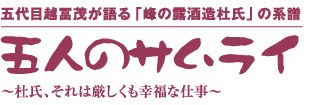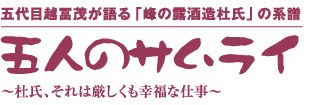峰の露酒造は、どうして100年にもわたって焼酎づくりを続けることができたのか。その要因として、かなり早くから杜氏と蔵人(くらこ)をきちんと置いて、しっかりとした生産体制を敷いてきたことが挙げられると思います。
初代杜氏の横井宇作は、明治10年の生まれで、明治36年の創業の年からここの蔵に入り、二代目の大瀬甚藏を杜氏に育てあげ、昭和5年まで勤めています。この二人の先輩について、もちろん私はほとんど知りません。が、その焼酎づくりへの情熱が並々ならぬものであっただろうということは、いま工場の奥に眠っている古酒の出来映えなどからみても容易に想像できますね。文句なく素晴らしい仕事をしていたはずです。
|
|

初代杜氏 横井宇作
明治10年3月10日生
入社 明治36年
退社 昭和5年

二代目杜氏 大瀬甚藏
明治24年2月17日生
入社 明治45年
退社 昭和19年
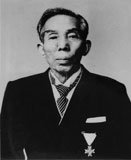
三代目杜氏 淋 豊嘉
明治35年11月12日生
入社 昭和2年10月1日
叙勲 昭和54年4月29日
●昭和53年11月、球磨焼酎作り
五十三年の功績により
現代の名工として労働大臣より
表彰される。
●昭和54年、勲六等瑞宝章を受ける。
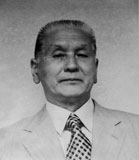
四代目杜氏 重富武春
昭和6年6月23日生
入社 昭和28年1月1日
|

三代目の淋豊嘉は、とにかく厳しい人でした。焼酎に向かう姿勢にも、どこか鬼気迫るものがありましたね。たとえば、「草履を履くと雑菌がつく」と言って、凍えるような冬の日でも裸足で仕事をするんです。まるでニワトリになったような気分でしたよ(笑)。
その三代目は、常圧蒸留にこだわっていました。これに対して、減圧蒸留を極めようとしたのが四代目の重富武春でした。一般的にいうと、常圧蒸留でつくった焼酎は香りが強く、甘味があります。しかし減圧の場合は、香りも甘味も抑えられてスッキリとした風味になる。こうした特性を生かして四代目がつくりあげたのが、お馴染みの「繊月」というわけです。現在、当社の商品ラインナップの中心となっている「繊月」「たる繊月」「舞せんげつ」は、重富杜氏の技術と経験と執念によって生まれた“焼酎の完成品”といえるでしょう。
|
|
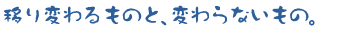
これは三代目にも四代目にも共通することですが、昔の杜氏は教えるということをまったくしないものでした。「見て覚えろ」が口癖で、何も言ってくれない。だから私たちは、いつも帳面を持って、それにメモしながら一つひとつ覚えていったものです。
昔の焼酎づくりは、いまの何倍もの重労働でした。それに加えて、そうしたやりかたで仕事を覚えさせられるわけですから、それはもうたいへんなものでしたね。
機械化が進み、酵母や麹の開発も進歩したおかげで、焼酎づくりの現場は大きく変わりました。しかし、変わらずにずっと受け継がれているものがあります。それは、「良質な麹づくりへのこだわり」と「徹底した温度管理」です。
麹は、一回一回、口に入れてみて確かめます。常に完璧な状態のものしか使いません。温度管理は季節ごとに変わる気温との戦い。相手は“生き物”ですから、ほんの少しでも気を抜くと命取りになるのです。
|
|
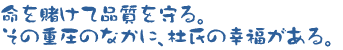
ここ数年、焼酎業界は大きく変わってきました。メーカー全体が向上し、お客さんの口も肥えてきて、本当にいいものしか受け入れられないようになっている。難しい時代だし、そういう意味では先の四人が経験しなかった戦いがあるわけですが、そこが五代目の私の腕の見せどころでもあるわけです。
「繊月」をはじめとする峰の露の焼酎がこれほど多くの焼酎ファンに支持されているのは、品質と味が常に高いレベルで安定しているからでしょう。その品質を、大袈裟でなく命賭けで守り、製品についてのすべての責任を背負う。それが、杜氏に課せられた使命であり、その重圧のなかに確かな幸福があるのです。
 |
|

四代目杜氏 重富武春と
五代目杜氏 越冨茂 |